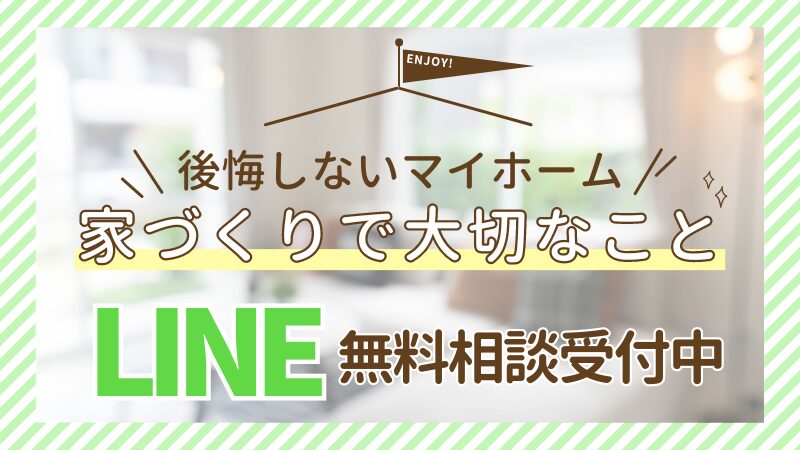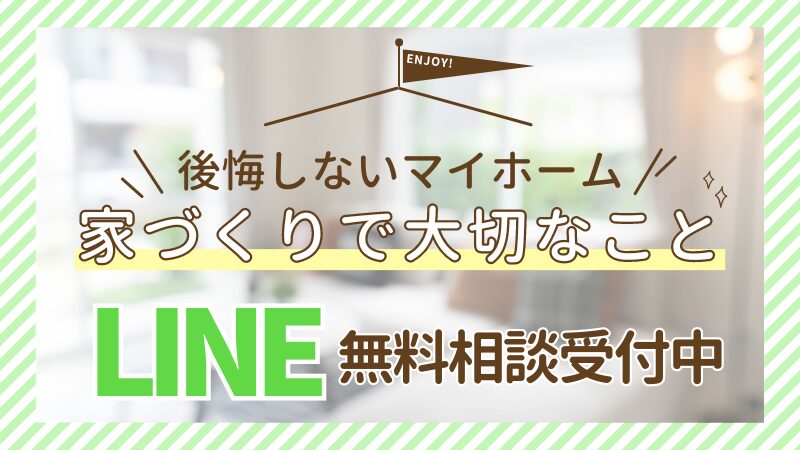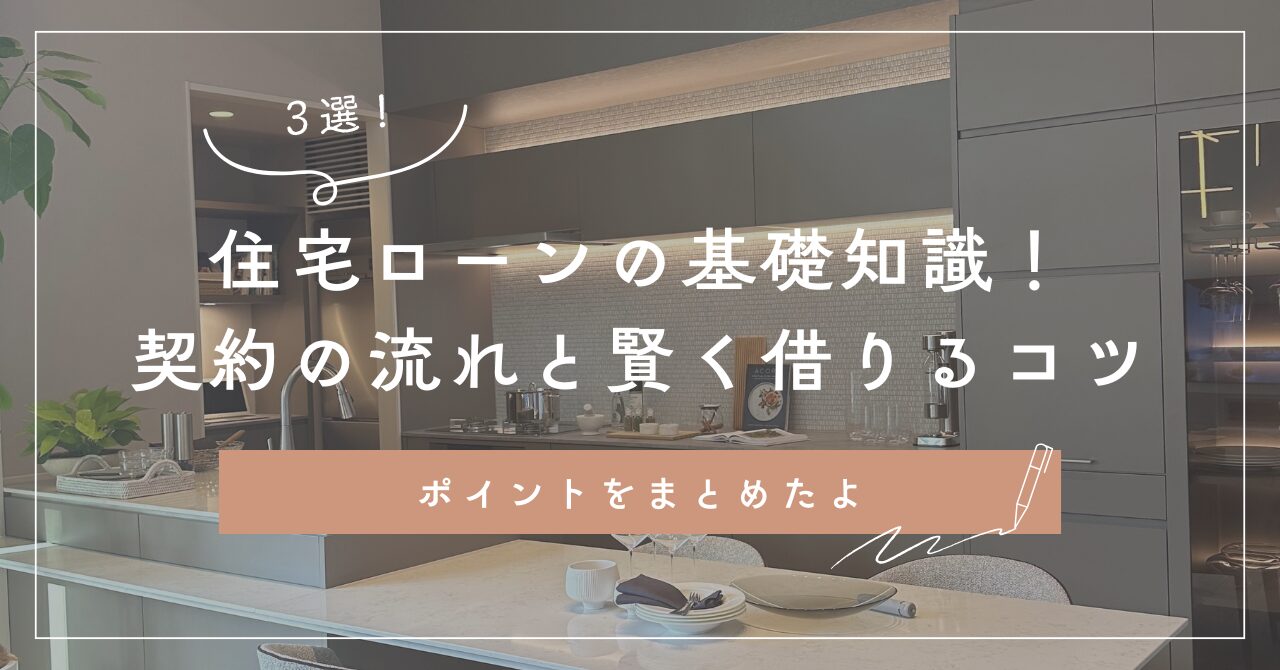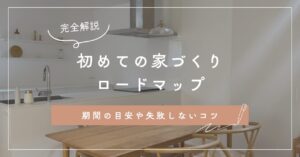家づくりにおける住宅ローン契約は、一生の返済計画を左右する重要なステップです。
 ゆゆ
ゆゆ銀行や金利の種類で返済金額も変わるから、慎重になるよね
この記事では、大手ハウスメーカー&不動産会社に勤務していた家づくりのプロ・かしゆうと、住宅ローンの基本について解説します。



住宅ローン契約は、家づくりと同時に進めていきましょう!
審査~融資実行までの流れや、必要書類、ローンの選び方のポイントまでお伝えしていきます。
住宅ローン契約までの流れ5ステップ
まずは、住宅ローンの契約の流れを見ていきましょう。
主な手続きは、以下の5段階で行われていきます。
- ステップ1.予算決め
- ステップ2.事前審査(仮審査)
- ステップ3.本審査
- ステップ4.つなぎ融資・分割融資の手続き
- ステップ5.融資実行



住宅ローンの審査は、仮審査と本審査の2回行います
一般的に、住宅ローンの手続きは家づくりと同時に行わなければいけません。
審査にはそれぞれ1~2週間かかるため、準備はしっかりしておきましょう。



ローンの手続きが遅れると、引き渡しも遅れるため要注意です!



効率よく決めていくことが大切だね
そこで今回は、家づくりの流れに合わせて契約の流れをご紹介していきます。
ステップ1.予算を決める
まずは、家づくりにかけられる予算を決めましょう。
借入総額や頭金の有無なども、最初に決めておくことがローン計画では大切です。
後述しますが、予算の目安は「返済負担率」なども考慮していかなければいけません。
年収や家族構成、ライフプランなどから、無理のない返済ができる予算を立てていきましょう。
「予算の決め方がわからない」「無理なく返済できる借入額を知りたい」という方は、お金のプロ=FPに相談してみるのもおすすめです。



ゆゆ家も定期的にFPさんに相談してるよ♪
ステップ2.事前審査(仮審査)に申し込む
予算が決まったらハウスメーカーに概算見積もりをもらい、その額の借入が可能か事前審査(仮審査)を行います。
事前審査は、返済能力があるかどうか金融機関が簡易的にチェックするもの。
主に、年齢、年収、健康状態、勤務先、勤続年数、連帯保証人などが審査項目となります。
ここで、忘れてはならないのが金融機関の比較です。
住宅ローンの借入先は、大手銀行からネット銀行、公的機関までさまざまあり、わずか0.1%の金利でも返済総額が大きく変わります。



借りる額は同じなのに返済総額が高くなるのはもったいない!



借入先はご自身で自由に選ぶことが可能です
「どんな金融機関が利用できるのか知りたい」「調べ方が分からない……」という方は、無料の一括比較サービスの利用もおすすめ。



いくつもの銀行を調べなくてもいいから、間取り決めに割ける時間が増えるのはうれしい!
ステップ3.プラン決定・本審査に申し込む
事前審査をクリアできたら、家のプランを練り上げていきます。
ハウスメーカーと正式に工事請負契約を済ませ、いよいよ本審査の申し込みです。
本審査の通過後は、ローン契約を結んでから着工となるため、手続きは早めにしておきましょう。



事前審査をクリアしていても、本審査で落ちることもあります
本審査で落ちる原因は、次のような理由があるようです。
- 期間中に車や家具など大きな買い物をした
- 転職をした
- 未申告の借金があった
- 健康状態に問題があると判断された



もしダメだったら家が建てられないの?



安心してください!ほかの金融機関に申し込んだり、借入額を減らしたり、対策することで借りられる場合があります
ステップ4.つなぎ融資や分割融資の手続き
土地の購入費用や手付金、中間金なども住宅ローンに含めたい場合は、「つなぎ融資」や「分割融資」を利用します。



住宅ローンはあくまでも引き渡し後からの融資実行となるため、建物の完成前は上記のようなローンを組む必要があるためです。
つなぎ融資は、担保がなくても利用できる一方で金利が高いのが特徴。
分割融資は、住宅ローンと同様の金利で利用できる一方で、諸費用がかかる・取り扱い金融機関が少ないなど、それぞれにメリットとデメリットがあります。
自己資金が十分にあり現金で支払うケースや、契約金以外で複数の支払いが発生しないケースでは、いずれも必要のない手続きです。



お金の流れに疑問がある場合は、ハウスメーカーに確認してみよう!
ステップ5.引き渡し・融資実行
家が完成したら引き渡しが行われ、住宅ローンの融資実行がされます。
当日に金融機関から借入金が振り込まれるため、引き渡し日は原則平日になることを理解しておきましょう。



住宅ローン減税を利用する方は、入居した翌年に確定申告が必要になることもお忘れなく!
住宅ローンに必要な書類とは?



住宅ローンの申請は、たくさんの書類を金融機関へ提出します
スムーズに申請を行うためにも、どんな書類が必要なのか把握しておきましょう。
仮審査の場合
- 免許証などの本人確認書類
- 源泉徴収票
- 残高証明書(ほかに借入がある場合)
- 注文住宅や土地の資料・簡易見積もり
残高証明書は、車やクレジットカードのローンが残っている方が必要となります。
また、金融機関によっては上記以外の書類を求められることもあるようです。
仮審査をインターネット上で申し込んだ場合でも、本審査で原本の提出が必要となるため、最低限の書類は事前に用意しておくことをおすすめします。



上記の書類は金融機関を比較する際も使うことがあるので、揃えておくと便利ですよ!
本審査の場合
- 免許証などの本人確認書類
- 源泉徴収票
- 実印・印鑑登録証明書
- 住民票
- 健康保険証
- 注文住宅や土地の資料・詳細な見積もり
本審査は、仮審査よりも書類が増えます。
繰り返しになりますが、本審査が遅れると着工も遅れるため、用意できるものから準備しておきましょう。
住宅ローンを賢く借りるための3つのコツ



大切なお金だから、住宅ローンで失敗したくない!
そのためには、ハウスメーカーに任せっぱなしにしないことが大切です。
ここからは、自分にぴったりの住宅ローンを見極めるための3つのコツをご紹介しましょう。
金融機関を比較する
上述したように、ハウスメーカーと提携の金融機関を紹介されても、より自分たちに適した住宅ローンを組むことが可能です。



ハウスメーカーはあくまでも家づくりを行う会社だから、お金の知識に関しては正直イマイチなこともあるみたい……
住宅ローンは、代表的なものでも以下のような金融機関で取り扱われています。
| タイプ | 概要 | 特徴 |
|---|---|---|
| 財形住宅融資 (公的ローン) | 勤務先で財形貯蓄を1年以上継続 50万円以上の残高がある場合に利用できる。 5年固定金利。 | 利用するための条件は多め 借入額の上限は低い ローン審査はゆるい傾向 |
| フラット35 (公的+民間ローン) | 住宅金融支援機構+民間金融機関が提供。 35年固定金利。 | 固定金利がずっと続く安心感 利用するための条件は多め ローン審査はゆるい傾向 |
| 民間融資や提携融資 (民間ローン) | 大手銀行、地方銀行、信用金庫、ネットバンク、保険会社、住宅ローン専門会社など。 ハウスメーカーと金融機関が提携して取り扱うローンも。 | 上限額や金利タイプなど選択肢が豊富 ローン審査は厳しい傾向 団体信用生命保険への加入は必須 |



結局、どれを選べばいいのかな?
金融機関を比較する際は、金利はもちろん、審査項目や団信(団体信用生命保険)※の有無、特典や優待サービスの有無なども異なるため、しっかり比較しましょう。
※団信=ローン契約者が亡くなった場合などに、ローン残高が免除される保険のこと。3大疾病特約など、保障の範囲も金融機関のプランによって異なる。
「もっとも良い条件で契約したい」「何社も事前審査の申し込みをする時間がない」という方は、ぜひ無料の一括比較サービスを利用してみましょう。
モゲチェックは、元銀行マンなど住宅ローンのプロが提供するマッチングサービスです。NHKや日本経済新聞に特集されたこともあるので信頼感も◎
約700社の金融機関から一人ひとりにマッチする会社をリストアップし、事前審査の申し込みも代行します。



時間をかけずに、より多くの選択肢から選べるのはありがたい!
家づくりに加えて、子育てや仕事に忙しい方こそ、住宅ローンを賢く選択していきましょう♪
自分に合った金利タイプを選択する
また、多くの方が悩むのが金利タイプです。
金利タイプは「固定金利(全期間)」「変動金利」「固定金利(機関選択)」の3つあり、どの金利タイプを選ぶかによって返済額も変動します。
固定金利は金利が変わらない安心感がありますが、金利が高めに設定されているため、金利を抑えてローンを組みたい場合は変動金利を選ぶと良いでしょう。



住宅金融支援機構の調査では、変動金利を選択する方は例年約8割ほどという結果に。
とはいえ、変動金利は金利の動向を見誤ると、子どもの進学などお金がかかるタイミングで返済額がアップしてしまう…なんてことも考えられます。



将来を見据えた返済をシミュレーションすることが大事だね
「金利が上がっても返済していけるのか不安」という方は、住宅ローン選びと併せて資産形成の相談をしておくと安心。
無料のFP相談サービスでは、どのくらいのローンを組めば将来安心できるか、また現状の無駄な固定費など、お金の悩みを総合的に相談できますよ♪
借りられる額より「返せる額」が重要!
注文住宅の希望を叶えるために、心理的につい限度額いっぱいまで借りたくなる住宅ローン。
しかし、審査が通ったからといって無理をすると、後々返済が苦しくなるかもしれません。



住宅ローンは、「返せる額」を借りることがポイントです!
そこで目安となるのが、収入に対する年間の返済額の割合を算出した「返済負担率(返済比率)」です。
返済負担率は、以下の式で求められます。
【返済負担率(%)=年間のローン返済額÷年収×100】
金融機関では、返済負担率30~35%以下を審査基準にしているというのが通説です。



ただし、ゆとりを持って返済できる比率は20~25%といわれています。
また、上記の計算式は「額面」で計算されるパターンが多く、「手取りの年収」で計算するとより安心。



借入総額から逆算して計算してみてね!
まとめ:住宅ローンは無理のない返済計画を立てよう



住宅ローンは比較とシミュレーションが大事なんだね
計算は自分でもできますが専門知識が必要だったり、比較のために多くの時間をかけなければいけなかったり、家づくりと平行して行うのはなかなか大変です。



それぞれのプロに頼れるところは頼って、賢くローン選択をしていきましょう!
また、「予算に合うハウスメーカーって?」「見積もりはもらったけど、どこで減額調整すべき?」といった家づくり中の疑問は、公式LINEからも無料でご相談可能です。
公式LINEからご紹介したハウスメーカーでご契約いただいた場合は、紹介割引が適用されます!



お金も時間も無駄をなくして、一緒に理想の注文住宅を建てましょう♪